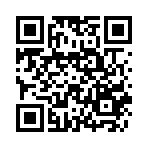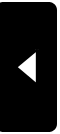2019年10月20日
大伴家持が愛した雨晴海岸(澁谷)
大友家持の愛した雨晴海岸

2155
バイクで訪ねる奥の細道(芭蕉が訪ねた季節に合わせて)
を実行する中で、越前、越中には5回ほど訪ねていますが
大伴家持を中心にしたことはありませんでした。
氷見常願寺の古い句碑
早稲の香や 右に曲がれば有磯海 芭蕉
残暑厳しい越後海岸を南下した芭蕉が
敬愛する大伴家持をたたえた句とされてる
私の解釈は
うまい越中の米と有磯海のぶりが食べたかった芭蕉の本音
http://cb400rdhp.cocolog-nifty.com/test/2009/05/post-6f08.html
そこで令和元年 万葉集に注目が集まるなか
越中高岡の万葉歴史館訪問、家持の句碑巡りをした次第です
大伴家持は越中の国司として2年滞在した際、万葉集に載せた歌など
223首を書き残したそうです
万葉歴史館(休館につき前庭のみ)

164
前庭の石碑 二上山の賦

2170

2171
気多神社の家持句碑
碑文は読めませんでした
馬並(な)めて いざ打ち行かな 渋谿(しぶたに)の 清き磯廻(いそま)に 寄する波見に
(巻17-3954・大伴家持)
現代語訳
馬を並べてさあ出かけようじゃないか。渋谿(現雨晴海岸)の清らかな磯に
打ち寄せているその波を見るために。
だそうです

2179

2189

2183
雨晴の家持の古い句碑
雨晴道の駅からきたへ100m右側の小さな公園 つまま公園
地元の有志が安政5年1860年に建立したとある
このころには万葉集が庶民にも浸透してた証拠とされてる
磯の上の つままをみれば 根をはえて
年深からし 神さびにけり
つままは楠の木
老木は 根が曲がっていて 神々しい

2195

2198
雨晴海岸
万葉歴史館hpより引用
現在は、JR氷見線や国道の開通により楽になった、伏木から氷見への道ですが、
松尾芭蕉が立ち寄った 頃でさえ、人のめったに通わぬ険しい道だったようです。
「渋谿」(しぶたに)は、その道の途中にあたり、二上山の山裾が海岸に落ち込んで、
日本海の荒波に洗われた数々の奇岩がそ そり立つ景勝奇岩の地です。
そして、その先には白い砂と緑の松林の松田江浜が続いています。
大和盆地に育った家持にとって、この景観は鮮烈なものだったと思われます。
ただし「渋谿」の地自体は、中世に奥州へ落ちのびる義経・弁慶主従が
ここの岩陰で雨宿りしたという伝説の方が 有名で、
現在もその伝説から「雨晴海岸(あまはらしかいがん)」と呼ばれています。
-雨晴海岸より見る雌岩-

2207
気多神社の家持歌碑文
https://ketaweb.com/category/gallery/
碑文
https://www.info-toyama.com/spot/80126/
万葉歴史館
https://www.manreki.com/
二上山の賦 解説
http://www5e.biglobe.ne.jp/~narara/newpage%2017-3985.html
雨晴道の駅
https://michinoeki-amaharashi.jp/

2155
バイクで訪ねる奥の細道(芭蕉が訪ねた季節に合わせて)
を実行する中で、越前、越中には5回ほど訪ねていますが
大伴家持を中心にしたことはありませんでした。
氷見常願寺の古い句碑
早稲の香や 右に曲がれば有磯海 芭蕉
残暑厳しい越後海岸を南下した芭蕉が
敬愛する大伴家持をたたえた句とされてる
私の解釈は
うまい越中の米と有磯海のぶりが食べたかった芭蕉の本音
http://cb400rdhp.cocolog-nifty.com/test/2009/05/post-6f08.html
そこで令和元年 万葉集に注目が集まるなか
越中高岡の万葉歴史館訪問、家持の句碑巡りをした次第です
大伴家持は越中の国司として2年滞在した際、万葉集に載せた歌など
223首を書き残したそうです
万葉歴史館(休館につき前庭のみ)

164
前庭の石碑 二上山の賦

2170

2171
気多神社の家持句碑
碑文は読めませんでした
馬並(な)めて いざ打ち行かな 渋谿(しぶたに)の 清き磯廻(いそま)に 寄する波見に
(巻17-3954・大伴家持)
現代語訳
馬を並べてさあ出かけようじゃないか。渋谿(現雨晴海岸)の清らかな磯に
打ち寄せているその波を見るために。
だそうです

2179

2189

2183
雨晴の家持の古い句碑
雨晴道の駅からきたへ100m右側の小さな公園 つまま公園
地元の有志が安政5年1860年に建立したとある
このころには万葉集が庶民にも浸透してた証拠とされてる
磯の上の つままをみれば 根をはえて
年深からし 神さびにけり
つままは楠の木
老木は 根が曲がっていて 神々しい

2195

2198
雨晴海岸
万葉歴史館hpより引用
現在は、JR氷見線や国道の開通により楽になった、伏木から氷見への道ですが、
松尾芭蕉が立ち寄った 頃でさえ、人のめったに通わぬ険しい道だったようです。
「渋谿」(しぶたに)は、その道の途中にあたり、二上山の山裾が海岸に落ち込んで、
日本海の荒波に洗われた数々の奇岩がそ そり立つ景勝奇岩の地です。
そして、その先には白い砂と緑の松林の松田江浜が続いています。
大和盆地に育った家持にとって、この景観は鮮烈なものだったと思われます。
ただし「渋谿」の地自体は、中世に奥州へ落ちのびる義経・弁慶主従が
ここの岩陰で雨宿りしたという伝説の方が 有名で、
現在もその伝説から「雨晴海岸(あまはらしかいがん)」と呼ばれています。
-雨晴海岸より見る雌岩-

2207
気多神社の家持歌碑文
https://ketaweb.com/category/gallery/
碑文
https://www.info-toyama.com/spot/80126/
万葉歴史館
https://www.manreki.com/
二上山の賦 解説
http://www5e.biglobe.ne.jp/~narara/newpage%2017-3985.html
雨晴道の駅
https://michinoeki-amaharashi.jp/
Posted by シルバーライダー二世 at 09:43│Comments(0)
│旅行