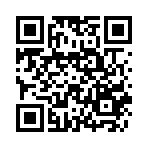2021年10月19日
日本のロゼッタストーンを訪ねる
日本のロゼッタストーンを訪ねる
大田原市湯津上 笠石神社の 国宝
那須国造碑(ナス クニノミヤッコ ヒ)

f2126

f2128
堂内の那須国造碑を撮った写真が不鮮明なので
ネット上の写真をお借りしました

f2136
八溝地区産の花こう岩
高さ 1.48m
幅 約50cm
厚さ 約42cm
19文字X8行
中国・六朝時代の気品ある書体
(私には 細い楷書風に見えた)
神社の宮司さんに声をかけるように案内板があり
声をかけると
宮司さん自ら 色々な資料を下さり説明してくれる
質問を交えながら 30分ほどの説明の後
碑堂に行き 鍵をあけてもらい 拝観した

f2132
花こう岩を磨きてん刻してある碑文は
書道のお手本にもなってるとか
詳細は以下のURLへ
https://www.city.ohtawara.tochigi.jp/docs/2013082778383/
https://www.tochigi-edu.ed.jp/furusato/detail.jsp?p=25&r=116
日本最初の考古学発祥の地とある

f2130

f2129
この碑文に
永昌元年 持統3年(689年)
評督 評の長官(大宝律令以後群と表示される)
の文字があり 7世紀の 律令体制が
黒羽の地まで 及んでいたことが解る
一級の考古学資料
これを発見したいきさつ
1676年 円順という僧侶がこの碑文を書き写し
徳川光圀が知るにおよび 碑の整備を命じる
水戸藩佐々介三郎が碑堂を作る
佐々介三郎はこの一帯にある 4世紀の
上侍塚古墳
下侍塚古墳
を発掘した
7世紀の古文書を実際に見られた
律令制度の一端が理解できる
黒羽の地域が那珂川の水に恵まれ繁盛していた
八溝山脈から流れてきた砂金が取れた
水戸光圀が整備をさせた
などなど 歴史が 身近に 感じられた瞬間でした
追記
本来の目的は
黒羽雲岩寺・芭蕉の句碑を訪ねる

0204

0220

0230
黒羽観光やなでアユを食べるでしたが

2098

2107

2113
秋の冴えわたる青空の元
良い一日を過ごすことができました
大田原市湯津上 笠石神社の 国宝
那須国造碑(ナス クニノミヤッコ ヒ)

f2126

f2128
堂内の那須国造碑を撮った写真が不鮮明なので
ネット上の写真をお借りしました

f2136
八溝地区産の花こう岩
高さ 1.48m
幅 約50cm
厚さ 約42cm
19文字X8行
中国・六朝時代の気品ある書体
(私には 細い楷書風に見えた)
神社の宮司さんに声をかけるように案内板があり
声をかけると
宮司さん自ら 色々な資料を下さり説明してくれる
質問を交えながら 30分ほどの説明の後
碑堂に行き 鍵をあけてもらい 拝観した

f2132
花こう岩を磨きてん刻してある碑文は
書道のお手本にもなってるとか
詳細は以下のURLへ
https://www.city.ohtawara.tochigi.jp/docs/2013082778383/
https://www.tochigi-edu.ed.jp/furusato/detail.jsp?p=25&r=116
日本最初の考古学発祥の地とある

f2130

f2129
この碑文に
永昌元年 持統3年(689年)
評督 評の長官(大宝律令以後群と表示される)
の文字があり 7世紀の 律令体制が
黒羽の地まで 及んでいたことが解る
一級の考古学資料
これを発見したいきさつ
1676年 円順という僧侶がこの碑文を書き写し
徳川光圀が知るにおよび 碑の整備を命じる
水戸藩佐々介三郎が碑堂を作る
佐々介三郎はこの一帯にある 4世紀の
上侍塚古墳
下侍塚古墳
を発掘した
7世紀の古文書を実際に見られた
律令制度の一端が理解できる
黒羽の地域が那珂川の水に恵まれ繁盛していた
八溝山脈から流れてきた砂金が取れた
水戸光圀が整備をさせた
などなど 歴史が 身近に 感じられた瞬間でした
追記
本来の目的は
黒羽雲岩寺・芭蕉の句碑を訪ねる

0204

0220

0230
黒羽観光やなでアユを食べるでしたが

2098

2107

2113
秋の冴えわたる青空の元
良い一日を過ごすことができました